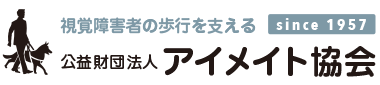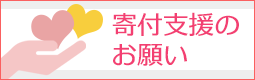クイズ形式で楽しく学ぶ、アイメイトのこと
見学日に参加していたのは、小学生のお子さんを連れた親子、大学生、ご年配の方など、参加者の年代もさまざま。この日は、協会スタッフや歩行指導員だけでなく、現役のアイメイト使用者さんも参加して一緒にお話ししてくれました。

まずは協会スタッフから、「いま、この会場に何人いるのか、アイメイト使用者さんに言葉を使わずに伝える方法はありますか?」という質問がありました。うーん……と首をかしげる参加者のみなさん。
「では、拍手してみてください」と言われて全員で拍手をすると、その音を聞いたアイメイト使用者さんが「20人くらいですか?」と人数をぴったり当てます。これには、会場から「おお!」というおどろきの声があがりました。
そのあとも〇×クイズ形式や映像などを視聴しながら、アイメイト協会の事業のこと、視覚障害のこと、アイメイト(盲導犬)のことについて楽しく学んでいきます。
〇×クイズで出された問題のひとつが「盲導犬は犬自身が道を覚えて、主人を案内する。マルかバツか?」 さあ、みなさんは答えられるでしょうか?(※答えは、このページの一番下のリンク先にあります)
意外と知らない!? 学びがいっぱい
アイメイトの訓練のこと、活動を支えるボランティアのことなど、知っているようで知らないことがたくさん。
アイメイト協会は日本で最初の国産盲導犬を送り出した団体ですが、創設者の塩屋賢一さんは、目の見えない世界を知るために一カ月間、目隠しをしながら生活したそうです。その間、足を踏み外してドブに落ちてしまったり、トラックのミラーに顔をぶつけたりもしたというエピソードに、参加者もびっくりした様子でした。
繁殖奉仕と呼ばれるボランティアのご家庭で生まれた子犬がアイメイトになるまでの流れや、アイメイトならではの泊まりこみでの4週間の歩行指導についても紹介します。
アイメイト(盲導犬)の歴史についての説明では、かつてはアイメイトを連れていると、ホテルやレストランで入店拒否されたり、バスなどに乗れなかったこともあったと聞きました。最近ではそうした入店拒否は減ったそうですが、「飲食店で入れてくれなかった経験はありますよ」とアイメイト使用者さん。だからこそ、視覚障害やアイメイトについて、みんなで学んで広めていくことが大事なんですね。
アイメイトの訓練の紹介では、実際に歩行指導員がアイメイト候補犬に声符(アイメイトへの指示に使う言葉)を使ってデモンストレーションしてくれます。
たとえば、「ドア」と指示すると、アイメイトはドアを探し、鼻先でドアノブの位置を示します。ほかにも落としたものを拾う「フェッチ」、待つように伝える「ウェイト」など、声符に従って行動するアイメイトの様子に目が釘付け!
アイメイト使用者さんが4週間の歩行指導に参加した時のお話も、ユーモアたっぷりで面白かったなあ。現役アイメイト使用者さんの経験談をいろいろ聞けるのもよかった!
参加者も誘導ロールプレイングをしてみよう!
参加者もいっしょになって「街中で視覚障害の人に出会ったら、どう声をかけたらいいのか」を、アイメイト使用者さんとロールプレイングする時間もあります。何か困っていそうだなと思ったら、まずは「何かお手伝いすることはありますか?」など声をかけることが大切だそう。
今回のロールプレイングのミッションは、アイメイト使用者さんに空いている椅子やテーブルの場所を案内すること。最初はすぐ近くに椅子があるのですが、だんだんと案内する場所が遠くなっていきます。果たして、参加者のみなさんは、うまくアイメイト使用者さんを案内できるでしょうか?

さらに、時計の文字盤に見立てた「クロックポジション」で、視覚障害のある方に方向や物の位置をお知らせすることも体験。イラストの内容をアイメイト使用者さんに言葉で説明しながら「どんな風に伝えたらわかりやすいだろう?」と考えていきます。
目かくしをして、アイメイトと歩いてみよう!
さて、楽しく学んだあとは、屋外でアイメイトとの体験歩行です。アイマスクをしたら、歩行指導員に教わりながら、実際に一人ずつアイメイトと歩きます。最初は大人も子供も、おっかなびっくりで緊張した様子。体験歩行を終えて戻ると、アイメイト使用者さんが「どうでしたか?」と声をかけてくれました。

「思ったよりスピードが速くて最初はこわかった。信頼感が必要なんだなと実感しました」。「見えないから犬を踏んでしまわないか心配だった。でも、アイメイトがちゃんとひっぱってくれて心強かった」など、いろいろな感想が出ていました。
アイマスクをすると、足裏の感覚や周囲の音の聞こえ方も違ってくるみたい。実際に歩いてみることで、気づくことがたくさんありますね
こうして、盛りだくさんの見学日があっという間に終了です。
最後に協会のスタッフさんが話していたのは、アイメイト協会の目的は、「目の見えない方の社会参加のお手伝い」だということ。今回体験したことを思い出して、街なかで目の見えない方に出会ったら「何かお手伝いすることはありますか?」と積極的に声をかけてみようと思いました!
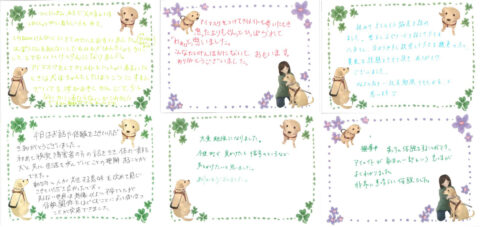
※本文中の○×クイズの答えはこちらから!
2025年7月2日公開