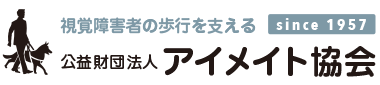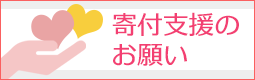日本視覚障害者卓球連盟 役員/静岡県STTクラブ所属 杉浦彰さん
60年前に盲学校で出会った卓球
杉浦さんはいつから卓球を始めたのでしょうか?
中学生のときに静岡県の盲学校に通っていたのですが、そのときにはすでに「盲人卓球」という呼び方で、ボールをネットの下に通して行う卓球がありました。大体60年くらい前ですね。でも、ルールも完成されていなくて、遊びでやる感じでした。最初はゆっくりしたスピードでやっていたので、実はあまり面白いと思えなかったんです(笑)。
高校からは東京の学校に行ったのですが、3年生くらいのときに、高校にも卓球台が入ったんじゃなかったかな。フレームが上げ下げできて、一般の卓球と盲人卓球の両用になっている卓球台だったのを覚えています。ちょうど東京オリンピック大会(1964年)があって、パラリンピック(※)が開催された頃です。
※大会の正式名称は「国際身体障がい者スポーツ大会」だが、このときに愛称として「パラリンピック」という呼び名が初めて使われた
オリンピック・パラリンピックの東京大会が開催されたときに、高校生だったのですね。
当時は今と違って、パラリンピックの選手は車椅子の人がほとんどだったんですよ。障害者スポーツへの認識もいまほどありませんでしたし、規模も小さなものでした。でも、その大会で視覚障害者の選手として卓球で優勝した人(※)が同じ高校の教員コースに入ってくることになって、それで学校に卓球台が置かれるようになったんです。
それまでお遊びのような卓球しかしたことがなかったので、すごい速さでパチパチと卓球をやっているのに驚きました。私ではとてもその人の相手にはならなかったんですけど、一本だけサーブを打ち返して嬉しかったことが記憶に残っていますね。寮の中での卓球大会はやりましたが、あの頃はまだちゃんとした卓球の大会は行われていなかったと思います。
※視覚障害者の卓球は国際競技ではなかったため、国内選手のみが出場した
その後もずっと卓球を続けていらしたんですか?
いや、卓球からしばらく離れていた時期も長いんです。20年弱くらい前に、山梨に住む元同級生から「山梨で独自に始まった新しい卓球があるから、大会に出ないか」と誘われました。それが「スルーネットピンポン」というものです。STTとも違う競技なのですが、そのときに初めて本当にスピードの速いやりとりをする卓球をしました。でも、全然打てませんでしたね(笑)。手元にボールが来ても手が動かない。そのくらいボールが速かったんです。
各地の大会でSTT仲間が増えていった
そこから、STTをやるようになっていくのですね。
1998年に日本視覚障害者卓球連盟という全国の競技連盟が設立されたのですが、その後、「盲人卓球」という名称が「STT」に変わりました。私が住む静岡県では2003年に国体が行われることが決まっていたのですが、「そこに向けて、静岡で卓球をやる運動をしませんか?」と他の人から誘われて、2001年にいまのSTTクラブの前身となる団体を一緒につくったのです。
当時は僕もうまくはなかったのですが、山梨に行ったり愛知や東京などにも行ったりしているなかで、どんどん仲間ができました。それで「こっちにも大会があるよ」、「あっちにも大会があるよ」と引っ張ってくれたので、大会に参加するうちに少しはできるようになっていきました。
静岡県の障害者スポーツ協会でもSTTを盛り上げようという機運が高まって、2003年の国体に間に合うように審判を養成したり、強化選手を選んだりしていきました。僕も強化選手に選んでもらいました。いまも静岡県STTでは、国体にあわせて行われる全国障害者スポーツ大会に出場する強化選手への指導を行っています。

杉浦さんがSTTを始めてよかったことは何でしょうか?
常に自分の目標をもつことができたことですね。早い時期に強化選手にしていただいたので、「大会で勝たなくちゃいけない」という思いを持って練習してきました。「ただ自分が強くなればいい」ということではなく、静岡県というものを背負って試合に出るんだという、そういう責任感をもつことが、自分にはとてもプラスになったと感じています。
高校時代にパラリンピックが行われたときには、障害者スポーツへの認識はあまり進んでいなかったということですが、社会の意識は変わったと思いますか?
僕が小学校に入ったときは、まだ戦後の混乱が残っていましたから、盲学校の存在もあまり知られていなかったし、親が目の不自由な子どもを学校に行かせないこともあるような時代でした。そういう部分では、かなり社会は変わったと思います。でも、まだまだだと思うことも多いですよ。
僕は卓球をしたり、野球をしたり、楽器を弾いたりもしますから、「すごい、見えないのに何でもできるね」と、最初はスーパーマンみたいに言う人もいるんです。でも、そのうちに当然、僕も失敗をしますよね。そうすると「やっぱり障害があるから」と言われてしまう。それは悔しいですよね。
目が不自由な人もそうではない人も失敗はするものですし、得意なことがあれば不得意なこともあります。それは同じことなんじゃないかな、と思うんですよ。もちろん目が見えないことが理由での失敗もありますが、「障害」というフィルターをかけずに相手のことを見てほしいと思います。

2020年9月23日公開